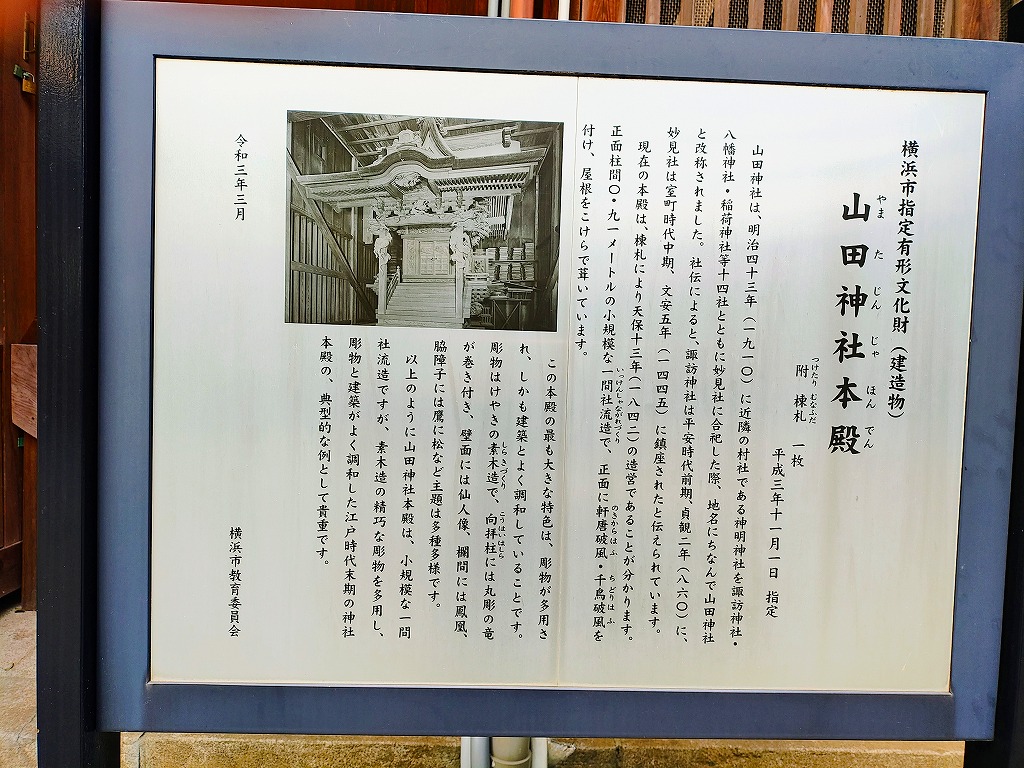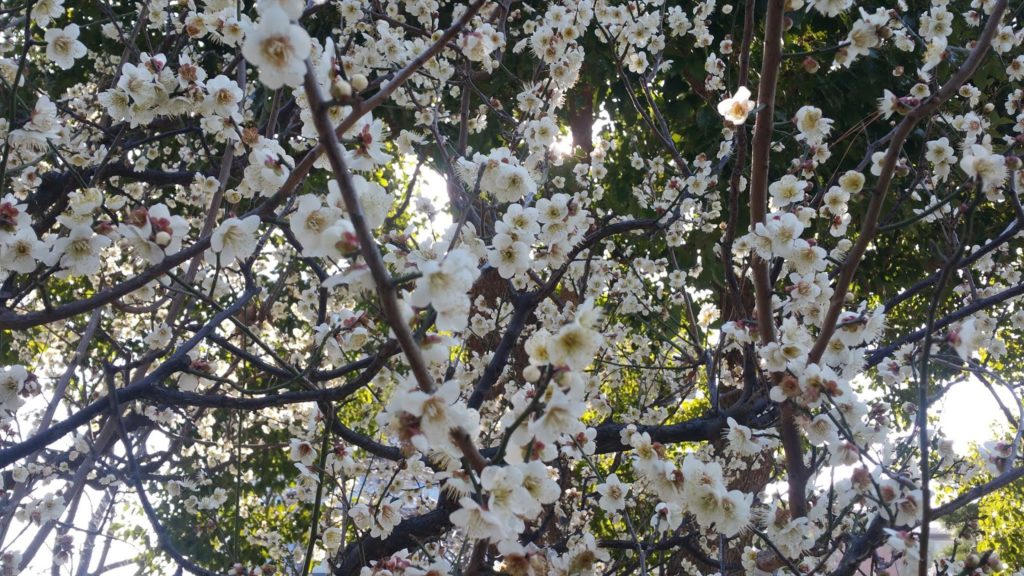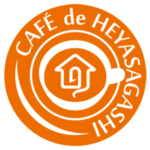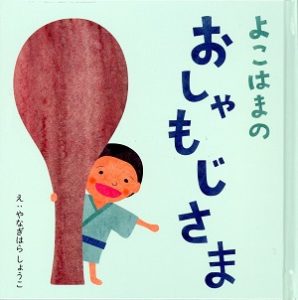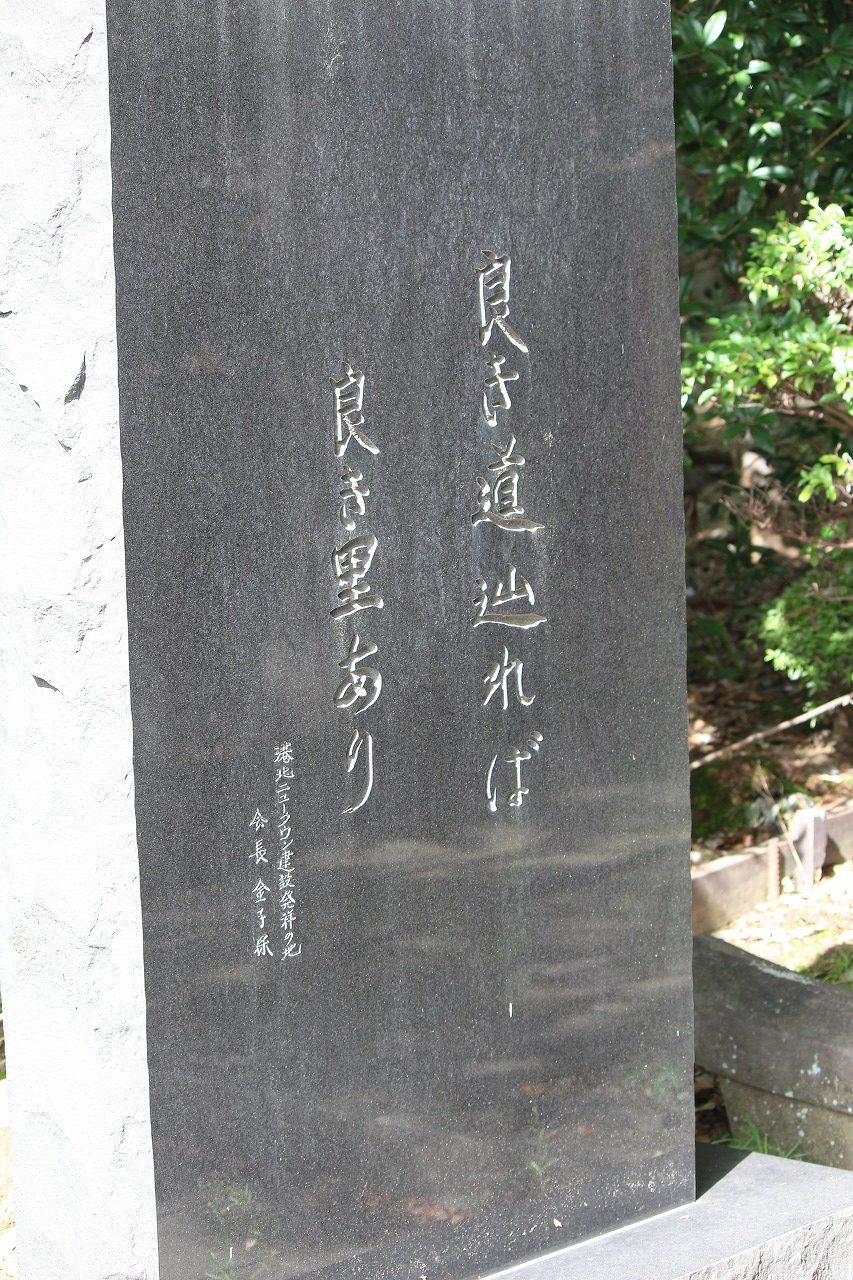花の寺、正覚寺の紫陽花は今真っ盛り 雨の日を彩る美しさ
雨が好き
今日は朝から雨。。しとしと降る雨が大好き。
「しとしと」音は心を静かにしてくれますし、余計な音も吸収してくれるような気がします。
私は6月生まれですし、雨は屋根も庭も草木も、、、何もかも洗い流してくれそうで好き。
ただ一つ、私のやっとの思いで毎日ドライヤーで伸ばしてくるくせ毛がその甲斐なく、クリクリ、モヤモヤになる点を除けば。。。笑

花の寺正覚寺の紫陽花
通勤途中に正覚寺さんに寄りました。雨の紫陽花が見たくて。

お寺に紫陽花って合いますね。
正覚寺さんは花の寺としても有名で、6月は菖蒲と紫陽花が真っ盛り。 見頃の時期です。
お寺の境内の左奥の山肌を埋め尽くすような紫陽花は圧巻です。
ほ~ら、紫陽花には雨がよく似合う。。。
ことに白い紫陽花が清楚で好きです。

正覚寺山門

お地蔵様

右手に7体のお地蔵様が迎えてくれます。

そして左手に7体の様々な石仏様。
鐘楼堂

大晦日には鐘を突けるそうです。
大晦日に鐘を突いたら良い年が迎えられそうですね。
阿弥陀堂(納骨堂)

安土桃山時代に開山
こちら正覚寺は、神奈川県横浜市都筑区にある天台宗の寺院です。
正式名は「長窪山総泰院正覺寺」。
文禄二年(1593年)=安土桃山時代、僧快栄上人の開いたお寺です。
文化年中に焼失し文化八年に再建。関東大震災で半壊し、大正十四年に修復。
只今本堂が建て替え中で仮本堂が建っています。
200年ぶりの建て替えで2024年から3年かけての工事だそうです。
仮本堂

十三参り
本尊は「虚空蔵菩薩」で、大日如来の福智の二徳をつかさどっている仏様です。
福智とは、福徳と智慧(善行による福徳と、悟りのための智慧)。
「智恵を授かる仏さま」なのですね。
十三参りとは13歳になった男女が、虚空蔵菩薩にお参りする習わしです。
昔は、数えの13歳は大人の仲間入りだったそうです。
ちなみに建て替え中「虚空蔵菩薩」は仮本堂に移設してあるようです。
大鷲神社

境内には、山王山大鷲神社、大鷲大明神が合わせて祀られています。
天台宗長窪山「正覚寺」
所在:神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東3-12-1
開門:9:00-17:00
アクセス:横浜市営地下鉄センター南駅から徒歩5分
公式HP:正覚寺