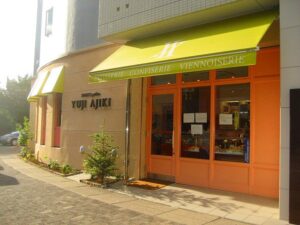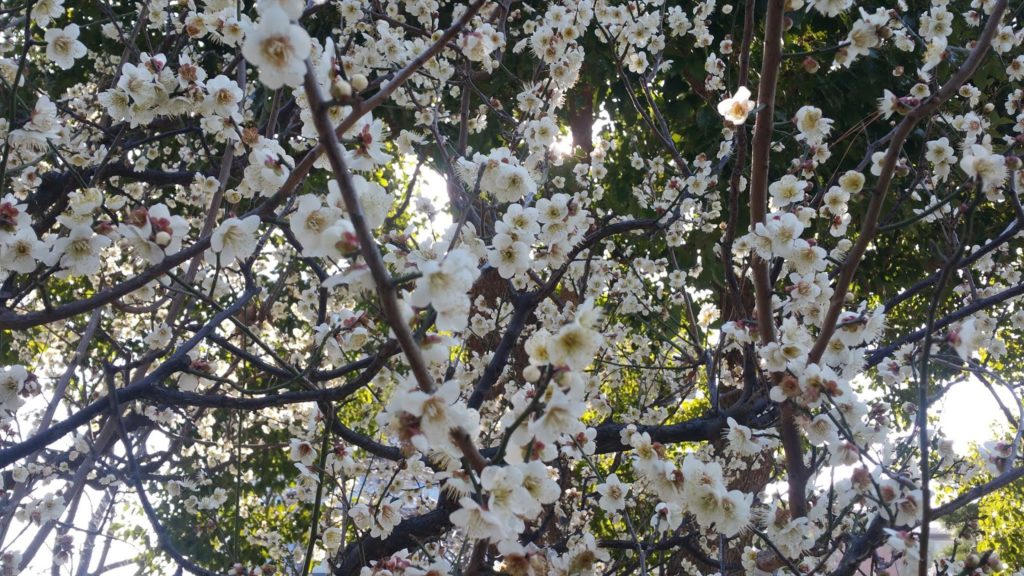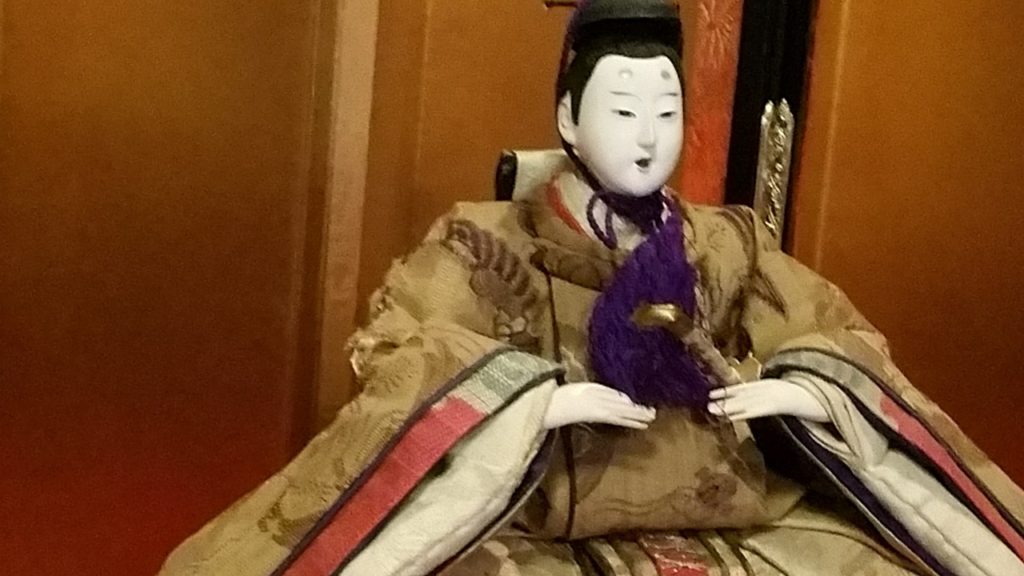長坂みねみち公園「カワセミ」は「飛ぶ宝石・翡翠」の名に相応しい
自然豊かな公園
長坂みねみち公園(横浜市都筑区)は、本当に自然豊かな公園です。
茅ヶ崎4丁目と長坂の境目に、細長く横たわります。
周りは雑木林で、池には鴨たちが泳ぎ、静かな環境で本当に幸せそうです。
好きな公園のひとつで、いつも通勤途中に車を止めて10分ほど過ごすだけですが、なんとも言えなくリフレッシュできます。
いつか、ゆっくり、徒歩で訪れたいものです。
カワセミに遭遇
ここでは、野鳥を撮るためか、カメラを構えた人を、よくみかけます。
今日は、偶然私も、カワセミに遭遇しました。
スズメよりちょっと大きめぐらいの大きさです。
付近は枯れた枝ですので、一際、目立ちます。
雄と雌は嘴で見分けるそうです。雄は黒、雌は赤。これは雄ですね?
何度か、山崎公園やせせらぎ公園で見かけましたが、ここでは初めて。
飛ぶ宝石
いつもカワセミを見ると、その美しさに感動します。
青の羽にオレンジ色の腹部。頭、頬、背中は青く、頭は白い鱗のような模様がある。喉と耳の周囲が白く、胸と腹と眼の左右は橙色。足は赤っぽい色。
まさしく「飛ぶ宝石」「翡翠(ヒスイ)」の名にふさわしい。
時々、水の中の獲物を狙ってダイブするのですが、それを撮るのは難しくて・・・。
次回は、ゆっくり時間をとってチャレンジしたいものです。